幸せの鍵は、本質にありとは。
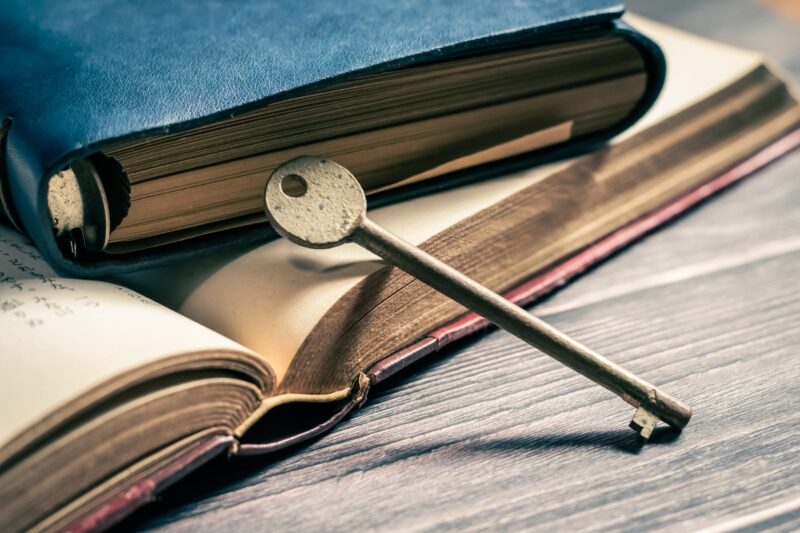
私は昔から、学校でも繊細過ぎて人付き合いより孤独を選び、以前、工場で働いてみたのですが、一見単純作業だけで良さそうなお仕事でも、対人関係は必要なので気疲ればかりしていました。
いろんな本を読んだり実践したりして生きていましたが、うまくいく実感を得られたものもあれば、そうでないものもあり、うまくいかないものの方が圧倒的に多かったです。
そんな中、色んな出版物を読み進める中で、「書かれてることは共通して似てるのになぁ」ということに気が付き、人類の長い歴史の中で磨かれ続けて今の時代にも残る、「普遍的な本質」を探求するようになりました。
本を読んでも情報を得ても知識を得てもあまり幸せになれない理由

近年は誰でも配信できるようになり、世の中は多くの情報や方法論が溢れています。
私自身も色んな「10ヶ条」や「3つの方法」なんていうものに飛びついてなんとかしようと思いましたが、次から次に出てくる情報に疲れ果てることもありました。
先に本質に気がつけば良かったのですが、情報や方法は何の為にあり、自分の幸せに本当に役に立つのか?そして、自分の幸せにどう活かすのか?という自問自答が一番大切な本質的な部分と気が付きました。
そして、この気付き自体は当たり前のことですが、当たり前のことをどれだけ本質的に理解しているのか?ということも重要と思います。
武経七書をテーマに選んだ理由
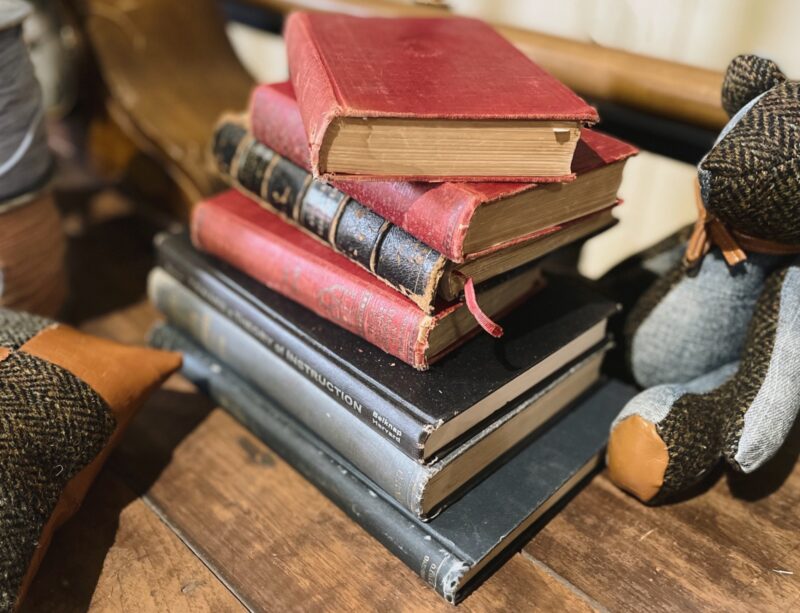
世界には、道徳面では聖書、仏教聖典、孔子の論語などがあります。
一方、生存競争に役に立つものとして、ランチェスターや孫子の兵法書、五輪書などがあります。
私は、以前、孫子の兵法書を読んだことがあります。
理由は、「戦わずに勝つ」とか「勝算がなかったら戦わない」という基本思想が、自分の身を守るのに役に立つかな?と思ったからであり、自分以外の他人や社会に対して活用することで、実際に身の守りになったことがあります。
今回は、孫子の兵法書だけでなく、もっと広義的に探究するために、武経七書(『孫子』 · 『呉子』 · 『尉繚子』 · 『六韜』 · 『三略』 · 『司馬法』 · 『李衛公問対』)を選択しました。
初めて孫子の兵法書に触れた時に、守屋 洋先生の翻訳のものを読みました。
守屋 洋先生の出版された書籍の中に、武経七書がありましたので、これを参考に本の内容ではなく、自分自身に対しての活用の感想等を書いていこうと思います。
この企画を通して自己成長し、さらには自分の気付きが誰かの幸せの指針になったり、新たな気付きのきっかけにつながりますように。


